

|
| |||
|
|
|
|
|
|
戦国の世では、どのような武器、防具を使っていたか |
|---|
|
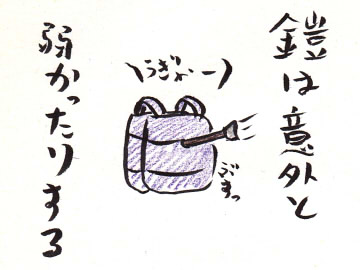
弓の威力は時代に応じて強化されていったので、いつからこの威力があるかはわかりませんが、南北朝の頃には鉄板を貫通できたようです。 ちなみに、平安末期の源平合戦では弓を持つ騎兵(武士)が戦いの主役でしたが、馬の上では命中率も低く発射速度も落ちるため、次第に徒歩で弓を射る弓足軽にその地位を奪われました。それ以後、日本において弓兵は基本的に徒歩の者で、戦国時代でもそうでした。 騎兵は弓ではなく槍や巨大な刀(野太刀)を武器を手に戦うことが増えました。とはいえ、騎馬弓兵が絶滅したわけではないとは思います。 さて、全世界共通なのですが、騎兵はその戦闘能力が非常に高いです。歩兵と比べると、時期や状況に応じて三倍、五倍、十倍の戦闘力を持つと言われています。そのため、南北朝の頃は騎兵突撃が猛威を振るったようで、平地では騎兵が最強の存在でした。 これを迎撃できたのが雑兵の弓だったのです。鉄板すら貫通する弓の威力は騎兵を撃退できる強力な兵器だったのです。ただ、近づかれると弱いので、平地では時として騎兵のパワーに蹴散らされました。 ただし、騎兵が動きずらい地形が多い日本では不整地戦も多く、南北朝時代の名将は時として騎兵を歩兵で打ち破っています。この頃から騎兵が徒歩で戦うことも多かったそうです、不利なところで馬に乗る意味がありませんからね。 騎兵は高い機動力を持っています。それに加え、突撃の際には自身の体重+馬の体重を加えた慣性パワーと大きなシルエットによる威圧感で歩兵を圧倒できる攻撃に特化した兵科でもあります。 しかし、大きいことは敵に狙われやすいことでもあり、防御力はカスみたいなものでした。それでも弓が主力の時代なら、距離が離れていれば重装甲の騎兵は防御力も兼ね備えた状態でした。 ------------槍の威力------------ さて、次に槍について見ていきましょう。戦国時代に使われた主な槍は、4メートルを軽く超える長い槍、長柄槍でした。これは主に雑兵によって集団で使われる槍です。長く扱いにくい槍ですが、特殊な使い方をすることで、すさまじい威力を発揮しました。 
特殊な使い方とは、槍ぶすまと呼ばれる戦術です。歩兵に槍ふすまを作られると、騎兵はその歩兵に近づくことが出来なくなります。 動きが止まった騎兵はただのデカイ的なので、雑兵の弓で殺されることになります。こうして、不整地のみでなく平地でさえ歩兵は正面から騎兵に対抗できるようになりました。 ただし、長柄槍は長いために個人では扱いにくいものであるため、入り乱れて戦う乱戦には不向きなものでした。そのため、自由に動き回って戦う武将たちは持ち槍と呼ばれる短い槍を使用しました。 ------------槍と弓の相乗効果と鉄砲------------ 雑兵弓と長柄槍、この二つの武器の登場で戦場は歩兵が支配する時代となります。鉄砲が登場することでこの傾向はさらに加速しますが、それは別の機会にお話しましょう。 結論から言うと初期戦国時代の主力兵器は槍、そして弓でした。補助武器として刀や石が使われていました。鉄砲も最初は補助武器でしたが、次第に主力武器へと変貌していくことになります。 戦国時代の初期は槍と弓で戦場は支配されていましたが、後半は鉄砲こそが真の主役となっていました。織田信長が鉄砲を用いて武田騎馬軍団を撃破したとか、そのあたりのエピソードが有名ですよね。つまり鉄砲、これが歴史を劇的に変えました。 日本において火薬を使った兵器が使用されたのは、元寇が記録に残っている最古のものでしょう。つまり西暦1274年くらいのことです。この時、元軍は『てつはう』とかいう爆発兵器を撤退時に活用したそうです。 この後、日本で火薬兵器が登場するのは西暦1543年、種子島に鉄砲が持ち込まれた時だそうです。有名な話ですね。でも火薬兵器が日本で活躍したのは、実はもっと昔からだそうです。実際には応仁の乱で使われていたようで、当時の日記に『飛砲』とか『火槍』とかいう単語が転がっています。 さらに言うと、関東の英雄である北条氏康が幼児の頃泣き虫であったというエピソードで、外から聞こえてくる飛砲の音で「恐れて泣くこと限りなし」とかいうものがあるそうです。このような下地があればこそ、鉄砲伝来後に日本全土に鉄砲がものすごい速さで普及したのではないでしょうか。 鉄砲が戦いに与えた影響は大きく、まず騎兵の没落が加速しました。次に武士たちが身に纏う鎧にも影響を与え始めました。 結果、彼らの武装は鉄砲に対して抵抗力がある物へと変化していき、それは雑兵の鎧にも見られます。武器だけではなく防具さえにも変革をもたらした火薬兵器の威力には凄まじいものがあります。 次に進む 前に戻る |